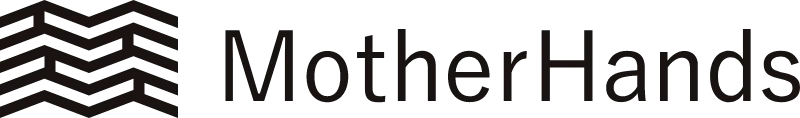「オウンドメディアは必要だとわかっているけれど、社内にリソースがない…」
「専門知識を持ったプロに任せたいけれど、どうすれば成功するの?」
このような悩みを抱えるオウンドメディアの担当者は少なくありません。オウンドメディアは継続的な運用が成功の鍵ですが、【人材不足】や【専門知識の壁】に直面することも多いのが現実です。
そこで注目されているのが「運用代行」という選択肢です。
ただし、ただ外部に丸投げするだけでは期待通りの成果は得られません。
このコラムでは、オウンドメディアの外注化を成功に導く5つの重要ポイントを解説し、運用代をこれから依頼する人が抱えるお悩みについて、プロからの回答をお答えしていきます。効果的なパートナーシップを築き、オウンドメディアの運用成果を最大化するヒントをお届けします。
目次
- 1 オウンドメディア運用代行のメリット
- 2 オウンドメディアの外注化を成功させる5つのポイント
- 3 オウンドメディア運用代行にまつわる《よくあるご質問》を5つのカテゴリーでご紹介
- 4 【オウンドメディア運用代行】コンセプト・必要性について
- 5 【オウンドメディア運用代行】運用代行サービスの内容について
- 6 【オウンドメディア運用代行】品質・実績・信頼性について
- 7 【オウンドメディア運用代行】運用面・スケジュールについて
- 8 【オウンドメディア運用代行】成果について
- 9 運用代行で自社の手間を無くし、より成果の出る運用を
オウンドメディア運用代行のメリット
自社でオウンドメディアを運用することも可能ですが、プロの運用代行を活用するメリットがあります。ここでは5つのメリットをご紹介いたします。
メリットその1)専門知識とノウハウの活用ができる
オウンドメディア運用には、SEO対策、キーワード分析、コンテンツマーケティング、ウェブ解析など多岐にわたる専門知識が必要です。代行サービスでは、これらの分野に長けた専門家チームが担当するため、最適なコンテンツ戦略の立案から実行まで一貫して高品質なサービスを受けられます。自社で同レベルの専門性を持つスタッフを育成するには時間とコストがかかりますが、代行サービスを利用することで即座に専門的なノウハウを活用できるのが大きな強みです。
メリットその2)継続的な更新と管理で”運用し続ける体制”が手に入る
オウンドメディアの成功には継続的なコンテンツ更新と管理が不可欠です。社内運用では他の業務優先で更新が滞りがちですが、代行サービスでは契約に基づき計画的かつ定期的なコンテンツ提供が行われます。また、過去コンテンツの見直しや改善、メタデータの最適化、リンク構造の管理なども継続的に実施されるため、時間の経過とともにメディアの価値や検索エンジンからの評価が高まっていきます。一度構築したコンテンツ資産を最大限に活用できる体制が整います。
メリットその3)成果測定と分析までお任せできる
プロフェッショナルな代行サービスでは、アクセス解析、コンバージョン分析、ユーザー行動分析など、データに基づいた効果測定を徹底して行います。これにより、何が効果的で何が改善すべきかを客観的に把握できます。単なるPV数だけでなく、滞在時間、直帰率、コンバージョン率など多角的な指標を用いた分析レポートを定期的に提出し、戦略の見直しや改善提案を行ってくれます。データドリブンな意思決定により、投資対効果の高いメディア運用が実現します。
メリットその4)最新トレンドへの対応が可能
デジタルマーケティングの世界は常に変化しており、検索エンジンのアルゴリズム更新やユーザー行動の変化に合わせた対応が求められます。代行サービスを提供する企業は複数のクライアントを抱え、常に最新情報にアンテナを張っているため、トレンドの変化をいち早く察知し対応することができます。自社だけでは追いきれない最新のマーケティング手法やコンテンツフォーマットを取り入れることで、常に効果的なメディア運用が可能になります。
メリットその5)複数チャネルの連携で1つのコンテンツを広く展開
効果的なデジタルマーケティングには、オウンドメディアだけでなく、SNS、メールマーケティング、広告など複数のチャネルを連携させることが重要です。代行サービスでは、これらのチャネルを統合的に管理し、相乗効果を生み出す戦略を立案・実行します。例えば、ブログ記事とSNS投稿の連動や、メールマガジンでのコンテンツ紹介など、各チャネルの特性を活かした効果的な情報発信により、ユーザーとの接点を増やし、エンゲージメントを高めることができます。
オウンドメディアの外注化を成功させる5つのポイント
オウンドメディアの運用代行を活用するメリットがお分かりいただけたところで、ここからは「オウンドメディアの外注化を成功させるポイント」についてお伝えします。
ただ外注するだけでは思うような成果は得られません。実際に外注化させるとなった場合にどのようなポイントを押さえておくべきか、5つに分けて紹介します。
ポイント①明確なゴールと評価指標の設定
オウンドメディアを外注する際に最も重要であることは、「外注先と成功の定義を共有する」ことです。この目的や定義にズレが生じてしまうと想定していた成果が得られない場合があります。
そのため、PV数、コンバージョン率、問い合わせ数など、具体的な数値目標を設定しましょう。「認知度を上げたい」といった曖昧な目標ではなく、「半年後にオーガニック流入を月間5,000PVにする」などの明確な指標があると、外注先も方向性を理解し、効果的な戦略を立てることができます。
ポイント②自社の強みや専門知識を共有する体制づくり
どんなに優秀な外注先・運用代行サービスでも、貴社のビジネスや顧客を完璧に理解しているわけではありません。貴社の意向に沿ったコンテンツづくりを行うためには情報共有が欠かせません。
定期的なミーティングや情報共有の場を設け、業界動向や自社の専門知識、顧客の声などを可能な限り積極的に提供しましょう。特に専門性の高い業界では、この情報共有が質の高いコンテンツ制作の鍵となります。また、オウンドメディア運用代行を行う企業は、外部から見た、いわゆるお客様目線の自社の強みやサービスの特徴などを提供してくれるはずです。このような体制づくりは、自社の強みやオリジナリティを出すためにも必要なプロセスです。
ポイント③適切なパートナー選びと契約内容の精査
「サービス内容や外注先の得意分野が自社のニーズにマッチするかどうか」を基準に選ぶことをおすすめします。単に安いだけの業者を選んでしまうと目的とは異なる結果になる可能性があります。価格だけではなく、自社業界への理解度や同業他社での運用実績、また外注することで解決させたい課題にどのくらいアプローチしてもらえるかなど、自社で必要なリソースを明確にした上で選定しましょう。
また、契約内容(納品物の範囲、修正対応回数、権利関係など)を事前に明確にして、後々のトラブルを防ぐことも大切です。相談しやすい外注先を選ぶことも不安を抱えない上で重要です。
ポイント④承認プロセスの効率化
外注化の大きなメリットは「効率性」ですが、社内の承認フローが複雑だと、そのメリットが失われてしまいます。迅速な確認・フィードバック体制を整え、修正依頼は具体的かつ建設的に行いましょう。
特に修正依頼を出す担当者が複数いる場合、担当者同士の共有体制も重要です。自社内で共有が行われていないと、何度も同じ依頼をすることになったり、別の担当者が出した指示を次の担当が覆すことになったりと依頼が進んでいきません。
意思決定者と実務担当者の役割分担も明確にすることで、外注先とのやり取りがスムーズになります。
ポイント⑤|継続的な改善サイクルの確立
オウンドメディアを運用する中で大事なことは「運用し続ける」ということでもあります。一度目標としていた結果が得られたとしても、運用をやめてしまえば結果は出なくなってしまいます。(他社も同じように運用しているため、追い越されてしまいます)
そのため、定期的なレポーティングやフィードバックを通じて、PDCAサイクルを回し続けることが重要です。データに基づいた分析結果を外注先と共有し、次の施策に活かす文化を作りましょう。運用代行先がデータを収集してくれる場合は、データ共有とミーティングをセットで行うこともおすすめです。
「依頼して終わり」ではなく、共に成長するパートナーシップの構築が長期的な成功につながります。
これらのポイントを押さえることで、オウンドメディアの外注化をより効果的に進め、期待する成果を得ることができるでしょう。外注化は単なる業務委託ではなく、専門知識を持つパートナーとの”協業”と捉え、互いの強みを活かす関係づくりを心がけることが、オウンドメディア成功の鍵を握っています。
オウンドメディア運用代行にまつわる《よくあるご質問》を5つのカテゴリーでご紹介
オウンドメディアの運用代行サービスを活用する際に、いただくお悩みをまとめてみました。主に5つのカテゴリーに分けられます。
◼︎コンセプト・必要性について
◼︎オウンドメディア運用代行サービスの内容について
◼︎品質・実績・信頼性について
◼︎運用面・スケジュールについて
◼︎成果について
同じお悩みであれば解決もスムーズに行うことができます。また、回答に対して「もっと詳しく知りたい!」という場合にはお気軽にお問い合わせください。
【オウンドメディア運用代行】コンセプト・必要性について
質問:ホームページに情報が載っていれば、記事って書かなくてもいいのでは?
回答:もったいないです!記事を書くことでお客様と繋がりを作ることができます。
ホームページは「会社案内」や「サービス紹介」が中心ですが、記事は「読者の疑問や悩みに答える」役割を持っています。つまり、記事を公開することで検索されやすくなる・信頼感が高まるなどの効果があり、ホームページだけでは伝えきれない情報を補うことで集客やお問い合わせにもつながります。
質問:SNSとどう違うんですか?ブログやコラムは必要ですか?
回答:役割が異なります。ブログやコラムは「情報の資産化」が可能です。
SNSは流れが早く、情報がすぐに埋もれてしまいます。一方でブログやコラムは、検索に残る情報として「資産化」でき、長期間にわたって読まれ続けるのが強みです。顧客の疑問に答えたり信頼を築くうえで、ブログ記事はとても効果的なのです。
質問:会社として発信していい内容なのか分かりません…
回答:「お客様に役立つ情報かどうか」で判断してみてはどうでしょうか?
発信の範囲に迷う場合は、「お客様に役立つ情報かどうか」で判断するのがおすすめです。製品やサービスの紹介に限らず、業界の豆知識やよくある質問などの手軽なところから始めるのも良いでしょう。
まずは社内で「伝えていいこと・NGなこと」をルール化すれば、安心して運用できます。ご希望があれば発信方針の設計もサポート可能です。
質問:オウンドメディアって流行りものじゃないの?今さら始めて効果あるの?
回答:オウンドメディアは流行りものではなく、基盤となる情報資産になります。
オウンドメディアは一時的な流行ではなく、「自社の情報を資産として残す」ための基本的なマーケティング手段です。短期的に結果をもたらすSNSとは違い、検索され続ける記事は長期的に価値を生み出します。
今から始めても遅くはなく、むしろ今のタイミングで整えておくことで今後の集客基盤になります。
質問:会社のブランディングにつながるのか実感が持てません…
回答:オウンドメディアは「言葉でブランディング」することです。
オウンドメディアは「言葉でブランディング」できる有効な手段です。丁寧に作られた記事は、企業の誠実さ・専門性・雰囲気を自然に伝えることができます。特に採用や営業の場面で、「御社の記事を読んで印象が変わった」と言われることも少なくありません。継続するほど効果が表れます。
【オウンドメディア運用代行】運用代行サービスの内容について
質問:記事の代筆って、具体的にどこまでやってもらえるんですか?
回答:お任せいただけるのであれば企画・構成・執筆まで全て請負います。
ヒアリングをもとに、テーマの提案から構成、執筆、画像選定、CMSへの入稿までワンストップで対応可能です。「伝えたいことはあるけど書くのが苦手」という方でも、インタビューをさせていただき記事にまとめられるようなスタイルもご用意しています。
質問:過去に書いた記事を活かしてもらうことはできますか?
回答:はい、過去記事のリライトや加筆、内容のブラッシュアップも得意としています。
もちろんです!リライトをすることで今まで作ってきた記事という資産を活かすことができます。
弊社は過去記事のリライトや加筆、内容のブラッシュアップも得意としています。内容が古くなっていたり、検索順位が伸び悩んでいる記事を、今の検索ニーズに合うよう改善することで、再び成果を出すことが可能です。コストを抑えつつメディア価値を高めたい場合にもおすすめです。
質問:ライターはどんな人が担当しているのですか?専門性がない方は困るのですが…
回答:大丈夫です。最適なライターを選定しています。
ご依頼いただく業種や記事の難易度に応じて、最適なライターを弊社で選定しています。医療・不動産・IT・教育など、各分野に精通したプロライターが在籍しており、案件ごとに経験や実績を考慮してアサインを行っております。業界でライティングをしてきた経験者となりますのでご安心ください。
質問:記事のネタ出しもお願いできますか?
回答:もちろん可能です。複数のテーマをご提案いたします。
もちろん可能です。業界トレンドや季節性、よく検索されているキーワードなどをもとに、複数のテーマ案をご提案いたします。お打ち合わせで方向性をすり合わせたり、「全てお任せ」スタイルで進めたりと、柔軟な対応が可能です。ネタ切れやアイデア不足に悩む必要はありませんので安心してお任せいただけるはずです。
質問:公開後の反響や数字も見てもらえますか?
回答:ご希望があればデータをレポート形式でご提出いたします。
ご希望があれば、記事ごとのアクセス数・滞在時間・検索キーワードなどのデータをレポート形式でご提出いたします。定期レポートだけでなく、改善提案も含めてフィードバックが可能です。効果が出ている記事・そうでない記事を分析し、次回以降の方針に活かせる仕組みを整えています。マーケティング会社だからできることです。
【オウンドメディア運用代行】品質・実績・信頼性について
質問:専門的な内容でも対応してもらえますか?
回答:はい、お任せください。一般のお客様にも伝わる記事作成を行います。
はい、可能です。専門性の高いテーマでも、事前に丁寧なヒアリングを行い、情報を正確に咀嚼したうえで一般の方にも分かりやすく伝える記事に仕上げます。必要に応じて貴社のチェックを挟むことで、内容の精度もしっかり担保します。
質問:こちらの考えやニュアンスをちゃんと反映してもらえるのでしょうか?
回答:事前の打ち合わせですり合わせ、公開前チェックにてご確認いただけます。
はい。事前の打ち合わせや記事案の段階でしっかりすり合わせを行うため、ニュアンスのズレが起こらないようにしています。納品前の確認・修正も可能なので、貴社らしい言葉や雰囲気を大切にした記事制作が実現できます。
質問:品質にバラつきが出たりしませんか?
回答:大丈夫です。社内にはたくさんのネタが眠っています。
記事制作は企画・ライター・編集者・チェック担当の4段階で確認する体制を整えています。さらに、案件ごとに運用マニュアルがあり、品質基準や表現ルールを明文化して対応しています。
万が一バラつきがあった場合も、記事のご確認時に修正・改善が可能ですので、安心して運用代行をご利用ください。
質問:うちの業界は特殊だけど、本当に対応できますか?
回答:特殊な業界やニッチなテーマにも対応可能です。
はい。特殊な業界やニッチなテーマにも多数対応実績があります。難しい専門用語や業界特有の事情がある場合でも、事前のヒアリングや資料のご提供を通じて、内容をしっかり理解したうえで記事化します。
また、業界に精通したライターを選出し、記事を作成しますのでご安心ください。ご心配でしたら必要に応じて細かな原稿チェックもお願いしておりますので、精度の高い記事に仕上げるためのご協力をお願いいたします。
質問:文章力だけでなく、マーケティングの視点もありますか?
回答:大丈夫です。社内にはたくさんのネタが眠っています。
もちろんです!単なる“文章の代筆”ではなく、「読み手の行動につながる導線設計」や「検索ニーズを意識した構成」など、マーケティング視点を重視しています。記事制作時にキーワードを設定しており、ユーザーから検索されやすいワード選定も行っております。
また、その他にも目的に応じて「問い合わせにつなげたい」「認知を広げたい」など、狙いに合わせた記事作成が可能です。ご相談しながら方針を決められますので、ご要望がありましたら遠慮なくお知らせください。
質問:記事を出して本当に成果が出ている企業はあるのでしょうか?
回答:はい、多くの企業様よりお声をいただいております。
多くの企業様で「検索流入が増えた」「問い合わせが2倍になった」「営業の提案材料として使えるようになった」など成果についてのお声をいただいております。
成果が出た企業の特徴として、継続して記事を出し、改善にも取り組んでいることが共通点として挙げられます。施策を正しく継続すれば、目指す効果はしっかり現れますので、運用を継続して行うことをおすすめします。
【オウンドメディア運用代行】運用面・スケジュールについて
質問:原稿の納品ペースはどのように決まるのでしょうか?
回答:月に何本の記事を出すかによってオーダーメイドにスケジューリングをいたします。
納品のペースついては、
・月に何本の記事を出したいか
・いつまでに公開したいか
・どのくらいの文字数を想定するか
など、貴社のご希望をもとにスケジュールを組みます。たとえば「毎月10日・25日に納品」など、あらかじめ定期日を決めておくと、そのタイミングに合わせて日程を組んでいきます。急ぎの案件にも柔軟に対応できるよう、余裕をもった体制を取っておりますのでご安心ください。
質問:記事公開までのスケジュール感が知りたいです
回答:記事公開の本数により異なりますが、おおよそ10営業日程度です。
初回ヒアリング後、記事1本あたりの制作期間は通常7〜10営業日程度が目安です。構成案の確認→執筆→初稿チェック→修正→納品という流れで進めます。
公開日が決まっている場合は逆算してスケジューリングいたしますので、「いつ公開したいか」からご相談いただくことも可能です。
質問:確認・修正の対応はどのタイミングでしてもらえますか?
回答:ご連絡いただいてから2〜4営業日内に行います。
原則として、ご指摘内容をもとに修正し、再提出まで通常2〜4営業日をいただいております。内容によっては1週間程度のお時間をいただくこともありますので、急ぎの修正が必要な場合は、事前にご相談いただけましたら幸いです。またその際には、即日対応も可能です。
修正の回数に上限は設けておりませんが、修正箇所があまりにも多い場合や内容を大幅に変更する場合には、作業費用を請求させていただくことがあります。作業前にご相談いたしますので、その際にご判断ください。
質問:月ごとにテーマや方向性を相談しながら進めたいのですが、可能ですか?
回答:
はい、可能です。毎月の初めに「記事企画ミーティング」や「チャットでのテーマ相談」の時間を設け、今月の方針をすり合わせてから進行することができます。ただし定例のミーティングにされるか、必要な時に都度のミーティングにされるかはご担当者様の状況を考慮しながら、逆にご提案をさせていただく場合もございます。
毎月のすり合わせを行うことができると、季節性や社内イベントなどに合わせたタイムリーな発信も実現しやすくなるため、柔軟な運用を行う体制が整います。
質問:月に出す本数が変更になることはありますか?
回答:自社都合で変更になることはありませんが、要望があれば変更可能です。
契約時に決まっていた本数を弊社が覆すことはありません。ただし、アクセス解析などのデータを分析した結果、本数について検討が必要だと判断した場合にはご提案という形でご相談させていただきます。
また貴社都合による本数の変動については可能な限り対応させていただいております。「今月は忙しいので2本に減らしたい」「キャンペーンに合わせて5本に増やしたい」といった変更にも柔軟に対応できます。月次契約の場合、一定の範囲内で本数を調整するケースも多く、過不足が出ないようにプランニングしますのでお気軽にご相談ください。
【オウンドメディア運用代行】成果について
質問:検索順位やアクセス数って、本当に上がるのですか?
回答:大丈夫です。社内にはたくさんのネタが眠っています。
すぐに成果が出るものではありませんが、SEOの基本を押さえた記事を継続的に発信していくことで、検索順位やアクセス数の改善は十分に期待できます。実際に多くの企業様で、中長期で運用をした結果、2倍以上のアクセス数を獲得することができています。
また、上がったキーワードや記事ごとの閲覧数も定期的にご報告することも可能です。
質問:どれくらいの期間で成果が出てくるものですか?
回答:中長期のスパンで効果測定をすることで成果が見えてきます。
一般的には、3~6ヶ月ほど継続して記事を更新していくことで、検索流入や認知の変化が見られるケースが多いです。1~2ヶ月では目に見える成果は出にくいですが、コンテンツが積み重なることで資産としての価値が高まり、半年〜1年で確かな手応えが感じられるようになります。
質問:成果って具体的にどんな指標で見ればいいですか?
回答:成果を何とするかは、目的によって異なります。一般的には…
主な成果の指標としては、
・ページの閲覧数(PV)
・検索順位
・問い合わせ数
・滞在時間
・直帰率
などが挙げられます。これらの指標を成果とするかどうかは目的に応じて変わりますが、例えば「資料請求につながった記事」や「問い合わせ導線からの流入数」など、具体的な行動と結びつけて評価することが重要です。
質問:記事が成果につながっているか、どうやって確認するのですか?
回答:専門の解析ツールを用い、データを抽出します。
Googleアナリティクスやサーチコンソールなどのツールを使って、どの記事がどれだけ読まれているか、検索流入がどのキーワードから来ているかを可視化できます。さらに、フォームや資料請求ページへの導線と組み合わせておけば、記事がどのように成果に貢献しているかが明確になります。
データを回収できるような設計を最初から行っておくことが必要不可欠です。自社に実装されていない場合はすぐに最低限の解析ツールの導入をおすすめします。
質問:思ったような成果が出なかった場合、改善してもらえますか?
回答:はい。分析をしながら改善を行い、PDCAを回して精度を高めていきます。
もちろんです。定期的なアクセス解析レポートをもとに、「読まれていない記事」「直帰率が高い記事」などを分析し、リライトや構成改善をご提案します。その際に、検索キーワードの見直しやターゲット変更などを行うことも可能です。
オウンドメディアで投稿する記事はPDCAを回しながら精度を高めていくのが正しい運用方法です。そのまま書いて放置しない、ということをマザーハンズでは大切にしています。
質問:記事の質が高ければ自然と成果は出るものでしょうか?
回答:検索意図にあっているか、動線を意識することも必要です。
質の高い記事は大前提ですが、それだけでは不十分な場合もあります。そしてその質の高いという基準は誰が基準であるのかを意識することも必要です。なぜなら質が高い記事=ユーザーに読まれる記事=ユーザーが求めている情報が載っている、ということだからです。
つまり検索意図に合っているか、導線が適切か、他の記事とどう連携しているかといった「ユーザー目線に合わせた全体設計」が重要です。また、記事をSNSやメルマガで紹介するなど、露出の工夫も合わせて行うことで、より成果につながりやすくなります。
質問:成果が出た後は、記事の運用をどう続ければいいですか?
回答:大丈夫です。社内にはたくさんのネタが眠っています。
成果が出た記事は「リライト」「関連記事の展開」「他の導線との連携」などでさらに強化することができます。また、成果が出ていない記事との違いを分析することで、今後の方針をより精度の高いものにできるでしょう。運用代行では、こうした継続的な戦略設計と改善提案も一括でサポート可能です。更新し続けることで、自社の運用成果を長く保つことができますよ。
運用代行で自社の手間を無くし、より成果の出る運用を
オウンドメディアは専門性の高い業務を社内だけで完結させることが難しい場合、そのまま放置するのではなく【運用代行サービス】を活用することをおすすめします。
専門家の知見を取り入れながら自社の負担を大幅に軽減し、本来のビジネス活動に集中できる環境が整い、メディアの質と継続性が担保され、結果として見込み顧客の獲得やブランド価値の向上など、具体的な成果につながっていくでしょう。
御社のオウンドメディア戦略を次のステージへと進める一歩として、専門家との協業=「オウンドメディア運用代行サービスを活用すること」を検討してみてはいかがでしょうか。
適切な運用があってこそ、その真価を発揮します。自社の強みと外部の専門性を掛け合わせることで、これまで以上の成果を効率的に実現できるはずです。
本テーマのおすすめ参考サイト:https://bakuyasu.techsuite.co.jp/46935/