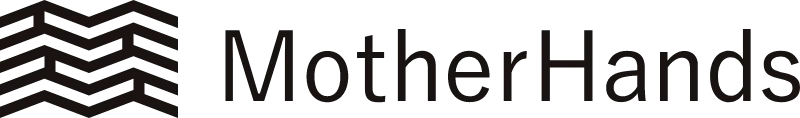オウンドメディアを始めたいけど、
「自社で運用すべきか外部に委託すべきか迷っている…」
「せっかく立ち上げたのに、なかなか成果が出ない…」
こんな悩みを抱えている企業担当者は少なくありません。
近年、自社の価値を発信し、顧客との関係構築を図るためのオウンドメディアの重要性が高まっていますが、その運用方法については多くの企業が試行錯誤を続けています。
自社リソースで運営するか、専門家に任せるか。
その選択によって、コスト、品質、そして最終的な成果は大きく変わってきます。
このコラムでは、オウンドメディア運用の二つの選択肢を比較し、あなたの会社に最適な運用方法を見つけるためのヒントをいただいた質問に回答する形でご紹介していきます。
目次
- 1 オウンドメディアとは?
- 2 オウンドメディアの自社運用と運用代行、どちらにする?
- 3 オウンドメディアの自社運用と運用代行のメリット比較
- 4 【オウンドメディアを自社運用する時】の疑問を解決!
- 4.1 質問:何を書いたら良いですか?テーマやトピックがすぐに無くなりそうです。
- 4.2 質問:どれくらいの頻度で記事を出せばいいですか?
- 4.3 質問:内容が他社と被ったり、似てしまいそうで不安です…
- 4.4 質問:専門的すぎて読んでもらえるかが不安です…
- 4.5 質問:運用を始めてからどれくらいで効果が出るものですか?
- 4.6 質問:成果が見えにくくて社内に説明しづらいのですが、どうしたら良いですか?
- 4.7 質問:SEOの知識がないので、検索に強い記事が書けないのですがどうしたら良いでしょうか?
- 4.8 質問:記事の更新が途切れてしまうのですが、何か良い方法はありませんか?
- 4.9 質問:公開した記事がほとんど読まれていないのですが…どうしてでしょうか?
- 5 【オウンドメディア運用代行サービスを活用する時】の疑問を解決!
- 6 自社運用・運用代行、迷ったらまずはご相談を
オウンドメディアとは?
オウンドメディアとは、企業や組織が自社で所有・運営するメディアのことを指します。主にウェブサイトやブログ、SNSなどのデジタルプラットフォームを活用し、自社のコントロール下で情報発信を行うことができます。従来の広告とは異なり、継続的なコンテンツ発信によって、潜在顧客との接点を増やし、ブランド認知や信頼関係の構築、そして最終的には顧客獲得につなげることを目的としています。
オウンドメディアの最大の特徴は【他社プラットフォームに依存せず、自社の判断で自由に発信できる点】です。長期的な視点での顧客獲得やブランディングに効果を発揮してくれます。
ブログやコラムも実はオウンドメディア?オウンドメディアの種類
「オウンドメディア」という言葉を聞くと、大規模なWebメディアを想像される方も多いかもしれませんが、実はブログやコラムも立派なオウンドメディアの一種です。オウンドメディアには様々な形態があり、企業の目的や予算、リソースに合わせて選択することが可能です。
主なオウンドメディアの種類としていくつかご紹介します。
1,企業ブログ・コラム
比較的手軽に始められるオウンドメディアとして、多くの企業が活用しています。専門知識の発信や、企業の取り組みを紹介することで、ブランドイメージの向上や顧客との関係構築に役立ちます。
2,コーポレートサイト
会社概要や事業内容、採用情報などを掲載する公式サイトも重要なオウンドメディアです。企業の顔として、信頼性や専門性を伝える役割を担っています。
3,オウンドメディアサイト
特定のテーマに特化したWebメディアを構築し、ターゲットユーザーに有益な情報を提供します。自社製品・サービスに直接関連しない情報も含め、幅広いコンテンツを発信することが特徴です。
4,メールマガジン
登録者に定期的に情報を届けることができる、直接的なコミュニケーションツールです。顧客との関係性を深める効果が高いとされています。
5,SNSアカウント
企業が運営するTwitter、Facebook、Instagramなどのアカウントも、広義のオウンドメディアに含まれます。気軽にユーザーと双方向のコミュニケーションが取れる点が魅力です。
6,YouTube/動画チャンネル
視覚的に情報を伝えられる動画は、製品デモンストレーションやハウツーコンテンツとして効果的です。
これらを組み合わせることで、より効果的な情報発信が可能になります。例えば、オウンドメディアサイトで詳細な情報を提供しつつ、SNSで誘導を行うといった連携戦略が一般的です。自社の目標やリソースに合わせて、最適なオウンドメディア戦略を検討することが重要です。
オウンドメディアはそもそも必要なのか?
「オウンドメディアって本当に必要なの?」
「うちの会社にとってどんなメリットがあるの?」
近年、マーケティング戦略として注目を集めるオウンドメディアですが、その必要性に疑問を持つ経営者や担当者も少なくありません。限られた予算とリソースの中で新たなメディアを立ち上げ、継続的に運用していくことへの懸念は当然のことでしょう。
しかし、オウンドメディアを持つことは、大きなメリットをもたらしてくれる可能性を秘めています。ここではオウンドメディアの必要性を3つのポイントにまとめてみました。
①自社主導のブランドストーリー発信で顧客との信頼関係を構築できる
オウンドメディアは、他社プラットフォームやメディアに依存せず、自社の管理・判断で情報発信できる場です。これにより、企業理念やブランドストーリーを一貫性を持って発信し、自社の価値観を正確に伝えることができます。広告やPRと異なり、中長期的な視点での情報発信が可能なため、顧客との深い信頼関係構築につながります。
②一度作った記事がマーケティング資産として残り続け、長く役立つ
一度作成したコンテンツは継続的に価値を生み出す資産となります。SEO対策されたコンテンツは長期間にわたって検索流入を獲得し続け、時間経過とともに蓄積されるコンテンツの総量が増えることで、企業の専門性や信頼性を示す証拠となります。一時的な広告とは異なり、投資対効果が継続的に向上する点が大きな魅力です。
③顧客接点の拡大とデータ収集ができる
オウンドメディアは潜在顧客との接点を大幅に増やす役割を果たします。購買意欲が高まる前の情報収集段階からユーザーにアプローチでき、購買検討を促進できます。さらに、アクセス解析やユーザー行動の分析を通じて、顧客の関心や課題に関する貴重なデータを収集できるため、製品開発やマーケティング戦略の改善に活用できる情報源となります。
オウンドメディアの自社運用と運用代行、どちらにする?
さて、ここまででオウンドメディアの役割や必要性についてご理解いただけたかと思います。
では実際に運用するとなった場合、オウンドメディアの運用方法として「自社運用」と「運用代行」の2つの選択肢があります。どちらを選ぶべきか悩んでいる方に向けて、それぞれのメリットを比較していきますので、自社の状況に合った最適な運用方法を見つける参考にしてください。
オウンドメディアの自社運用と運用代行のメリット比較
自社運用のメリット
①コスト効率が良い
外部委託費用が発生しないため、初期投資を抑えることが可能です。自社のサービスや商品、企業文化を熟知しているため、より深い洞察に基づいたコンテンツ制作ができます。
②即時対応が可能
市場変化や緊急事態に対して、決裁プロセスを短縮し、素早く対応できます。状況に応じて優先順位を変更し、リソースを柔軟に割り当てることができます。
③ノウハウの社内蓄積ができる
運用を通じて得た知見やスキルが社内に蓄積され、長期的な資産となります。
運用代行のメリット
①専門的な知識とスキルを活用できる
SEO、コンテンツマーケティング、デザインなど各分野の専門家によるクオリティの高い運用が可能です。
②リソース確保の安定性が高い
人材不足や社内リソースの変動に左右されず、安定した運用が期待できます。
③最新トレンドへの対応が可能
業界の最新動向や技術変化に常にアップデートされた知識でコンテンツ制作が可能です。
④客観的な視点=ユーザー目線のコンテンツ制作ができる
社外からの視点で自社の強みや魅力を再発見し、顧客目線に立ったコンテンツ制作ができます。
⑤実績に基づく戦略
複数の運用実績から得たデータや知見を活かした効果的な戦略立案が可能です。また、メディア運用のリソースを外部化することで、自社の本来の業務に集中できます。
どちらを選択するかは、自社のリソース状況、予算、スキルセット、そして長期的な目標によって異なります。また、ハイブリッド型の運用(一部を自社で行い、専門性が必要な部分を外部委託する)という選択肢もあります。迷ったらオウンドメディア運用の専門家に相談してみることも1つの手です。
【オウンドメディアを自社運用する時】の疑問を解決!
質問:何を書いたら良いですか?テーマやトピックがすぐに無くなりそうです。
回答:大丈夫です。社内にはたくさんのネタが眠っています。
「書くことがない」と感じるのは珍しくありませんが、実は社内にたくさんのネタが眠っています。お客様からの質問、サービスのこだわり、業界あるある、スタッフ紹介などが立派なコンテンツになります。読者の悩みや関心ごとを起点にすることで、ネタ切れせずに継続することが可能です。
質問:どれくらいの頻度で記事を出せばいいですか?
回答:目安としては月2〜4本が理想です。
目安としては月2〜4本が理想ですが、大切なのは「無理なく続けられるペース」です。たとえば、まずは月1本からスタートして、慣れてきたら徐々に増やすのも良い方法です。更新頻度が低くても、質の高い記事が定期的に追加されることで、検索エンジン対策や信頼構築にしっかり貢献します。
質問:内容が他社と被ったり、似てしまいそうで不安です…
回答:切り口や事例、語り口を工夫してオリジナリティを出しましょう。
テーマが似ていても、切り口や事例、語り口を工夫すれば自社独自のオリジナル記事になります。たとえば「よくある質問」に対して、自社の考え方や実際の対応方法を加えるだけで差別化が可能です。自社の体験や価値観を盛り込むことで、読み手に響くコンテンツになりますのでご安心ください。
質問:専門的すぎて読んでもらえるかが不安です…
回答:専門的な内容こそ、発信する価値があります。
専門的な内容こそ、わかりやすく伝えることに価値があります。難解な言葉や専門用語はなるべく噛み砕き、例え話や図解などを交えて伝えると、多くの人に届きます。むしろ「難しいことをやさしく説明できる会社」は信頼されやすく、問い合わせにもつながる傾向があるため、発信する意味は大きいです。
質問:運用を始めてからどれくらいで効果が出るものですか?
回答:一般的には3〜6か月、中長期的に効果を発揮していきます。
オウンドメディアは短期的な効果というより、中長期で成果が出る施策です。一般的には3〜6ヶ月ほどで検索からの流入や問い合わせがじわじわと増えてきます。急にアクセスが伸びるというよりは、少しずつ信頼が積み上がるイメージです。継続していくことで、会社の資産としても機能します。
質問:成果が見えにくくて社内に説明しづらいのですが、どうしたら良いですか?
回答:データの活用がマストです。
社内説明には、記事ごとのアクセス数や検索順位の変化、問い合わせに繋がった実績など「見える数字」があると効果的です。Googleアナリティクスなどの無料ツールで数値化できるので、簡単なレポートを月1回作るだけでも説得力が増します。「資産になる情報発信」であることも伝えると理解が得られやすいです。
質問:SEOの知識がないので、検索に強い記事が書けないのですがどうしたら良いでしょうか?
回答:SEO対策のポイントを押さえるか、運用代行の活用がおすすめです。
検索で上位に表示されるためには、キーワードの選定や見出し構成、記事全体の論理的な流れなど、いくつかのポイントがあります。専門的な知識がなくても、基本のルールを押さえれば十分な効果が期待できます。また、運用代行を活用すれば、SEOに強いライターや編集者が最適な構成で記事を作成するので安心です。
質問:記事の更新が途切れてしまうのですが、何か良い方法はありませんか?
回答:更新が途切れる原因を正しく理解しておく必要があります。
記事更新が止まってしまう原因は「ネタ切れ」や「担当者の忙しさ」が多く見られます。無理なく継続するには、事前にテーマをストックしておくことや、社内で役割を分担することが効果的です。運用代行を活用することで、継続的な記事配信を仕組み化でき、社内負担を大きく減らせます。
質問:公開した記事がほとんど読まれていないのですが…どうしてでしょうか?
回答:公開した記事の「分析」が必要です。
公開した記事が読まれない理由は、タイトル・内容・SEO・導線設計のどこかに原因があることが多いです。まずはアクセス解析を行い、読まれている記事との違いを把握することが第一歩となります。改善点が明確になれば、リライトや導線設計の見直しで成果につなげることができます。また、運用代行サービスにて、改善提案や記事のリライトも対応可能です。
【オウンドメディア運用代行サービスを活用する時】の疑問を解決!
質問:外注すると、自社らしさがなくなりそうで不安です
回答:ご安心ください。自社らしさを紐解き、形にいたします。
ご安心ください。運用代行では、まずヒアリングを通じて御社のトーンや言葉づかいを把握します。記事の方向性や表現の癖、伝えたい雰囲気などを共有いただければ、それを反映した原稿に仕上げます。納品前にはご確認・修正も可能なので、自社らしさを保った情報発信が実現できます。
質問:毎月同じような内容にならないか心配です
回答:幅広いテーマをご提案いたしますのでご安心ください。
代行サービスでは、業界トピック、季節性、読者の悩み、成功事例、スタッフ紹介など幅広いテーマをご提案可能です。記事が重複しないよう、過去の配信内容を管理しながら構成を調整します。また、定期的な企画ミーティングで方向性を見直すこともできるため、マンネリ化を防ぎやすい体制です。
質問:どこまで任せられるのか分かりません…。皆さんどこまで外注しているんでしょうか?
回答:お客様によって範囲はそれぞれですが、丸ごと任せるメリットがあります。
お客様によって外注の範囲はさまざまですが、企画から構成・執筆・校正・入稿・レポート提出まで、すべて丸ごと任せるケースが主流です。丸ごと任せるメリットとしては、一貫した継続運用が可能な点です。また、成果へのコミットなどを明確化させることもできます。
もちろん「執筆だけ」「構成と原稿チェックのみ」など部分的な依頼も可能ですが、情報の共有度合いによって確認などに時間がかかる場合があります。自社の体制やリソースに応じて、柔軟に設計・対応できるのが運用代行のメリットです。
質問:修正依頼や確認のやり取りが面倒そうです…
回答:運用開始時のルール設定により、手間を省くことができます。
確認や修正対応のフローは、運用開始時にあらかじめルール化します。例えば「記事案の確認は週1回」など、最小限の負担で進められる体制づくりが可能です。メールやチャットなど、使いやすいツールでスピーディにやり取りし、面倒なやりとりが続かないようサポートいたします。
質問:記事の方向性やテーマ選びは誰が決めるのですか?
回答:自社で力を入れたい分野をお知らせいただけましたら、弊社でも対応が可能です。
基本的には、弊社から御社に合った記事テーマや切り口をご提案し、ご確認いただく流れになります。もちろん「全部任せたい」「毎月相談しながら決めたい」など、運用スタイルに合わせて対応可能です。あらかじめ方向性や読者像を共有しておくと、よりスムーズに進行できます。
質問:SEO対策もしてもらえるのですか?
回答:SEO対策こそ、運用代行サービスを頼むメリットの1つです。
はい、もちろんです!SEOを考慮した記事構成やキーワード選定、検索意図に合った内容作りもお任せいただけます。検索エンジンだけでなく、実際に読む人にとってわかりやすく価値のある内容になるようバランスを重視しています。必要に応じて、検索順位や流入データのレポート提出も可能です。
質問:記事の内容は、毎回こちらでチェックできますか?
回答:はい、記事はほとんどの場合、お客様にチェックしてからの公開となります。
はい、すべての記事について、納品前に必ずご確認いただけるフローを設けています。初稿をご提出後、ご希望に応じて修正や加筆も可能です。「この表現は変更したい」「ここを詳しくしたい」などのご要望にも丁寧に対応します。記事の確認が不要な場合は「事前合意のうえで自動公開」といった運用も可能です。
質問:急な変更や差し替えには対応してもらえますか?
回答:可能です。ご相談いただければ対応方法をご提案いたします。
急なテーマ変更や記事の差し替えについても、可能な限り柔軟に対応いたします。スケジュールや進捗状況によっては一部調整が必要になることもありますが、事前にご相談いただければ対応方法をご提案いたします。社内事情や外部要因での変更にも、できる限り寄り添える体制を整えています。ただし、テーマが完全に異なる場合につきましては一部費用をご負担いただくようお願いしております。
質問:記事の公開や更新作業も代行してくれますか?
回答:記事の流し込みや公開作業まで代行が可能です。
はい、WordPressなどのCMSを活用した記事の入稿・公開作業も代行可能です。画像の挿入、カテゴリの設定、アイキャッチの調整など、細かな部分まで対応いたします。定期的な更新や公開スケジュールの管理も一括で行えるため、社内の負担を大幅に軽減できるのが特徴です。
自社運用・運用代行、迷ったらまずはご相談を
オウンドメディアの運用方法に正解はありません。自社の状況や目標、リソース、予算によって最適な選択肢は異なります。自社運用と運用代行、それぞれのメリットを理解したうえで、なお迷われている方は、まずは専門家への相談から始めてみてはいかがでしょうか。
マザーハンズは「本当に必要なものだけをご提案する」をモットーに、オウンドメディア運用の豊富な実績と経験を持って、企業様ごとの状況に合わせた最適な運用プランをご提案しております。初回相談無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
オウンドメディアを通じた効果的な情報発信で、長期にわたるマーケティング資産を形成していきましょう。